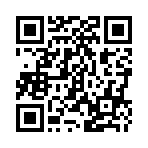2013年03月24日
オオクワガタ幼虫のバナナマット飼育
クワガタムシ飼育はだいぶ縮小した。昨年の春から飼育したのはオオクワガタを2セットだけだった。そのうちの1セットからは幼虫が5頭とれた。飼育容器はずっと屋外においてあり、温暖な浜松市でもエサはほとんど食べずにじっとしているようだったが、非常に小さい終齢幼虫で、春になったらそのまま蛹化しそうなので、小さめの容器に発酵マットを詰めて1頭ずつ分離した。
さてもう1セットのオオクワガタは、上記と同じように飼育していたのだが、いずれも亜終齢幼虫だった。数は11頭。手元の発酵マットが微妙に足りなさそうだったので、バナナマット飼育をすることにした。
バナナマット飼育とは、かつてパソコン通信の@Niftyにあった昆虫フォーラムで紹介されたものである。考案者は茗荷谷博士、追試を行ったのが史嶋桂さんだった。このフォーラムには勝手に昆虫フォーラムをライバル視していた別のフォーラムの「論客」がいて、面白く画期的な取り組みには茶々を入れて邪魔をし、建設的な議論になるのを妨害する輩がいた。やってもみないであんなモノは駄目だ、などという前に面白そうだからやってみようかな、という態度こそこのフォーラムにふさわしいはずで、実は私もヒラタクワガタ・ノコギリクワガタ・コクワガタで行い、納得できる成果が出た。要はいかに大きな成虫になるかということなのだが、結論からすると菌糸ビンには敵わないと思う。しかし無添加無発酵のマットに較べれば格段に大きく育つ。発酵マットとはかなり良い勝負になる。そこで私は折衷案をとって、バナナと発酵マットの組み合わせで、なかなか得難い大きさの成虫を羽化させ、喜んだものだ。
ではバナナマットとはどういうものか。これはクワガタムシの菌床飼育がまだまだコスト高だった時代に、初心者には難しかったのかも知れない発酵マット作成のリスクを避けるために、いくつかのマット飼育が試みられた。南方に移民した日本人が、漬け物を食べたいと思っても安定した発酵が得られないので、やむを得ずバナナをぬかどこにして発酵させた、という事実がヒントになっている。したがってこの時点ではマットを発酵させるためにバナナを使うという動機であった。そのあたりを詳しく記した史嶋桂さんのホームページがアクセス不能になっているので、事実上この飼育方法を紹介したものはなさそうだ。そこで手順を踏みながら以下に紹介してみる。

黄色いコンテナに入っているのはクヌギの廃ほだマットを小麦粉で発酵させたもの。これを容器の底に固めにつめておく。

小型の傷物のバナナ。定価以下で売っているもので十分。昔は傷物というと中身まで黒くなったものが売られていたものだが.....。

皮を剥いたバナナは充分きれいなものだった。だが傷物というにはまだ熟してもいないので、人の口にはあまり美味しくないかも知れない。

11頭の幼虫に対し用意できたバナナが10本だったので、適当にカットしておおよそ同じ分量になるようにバナナを分けて容器に入れる。

バナナを埋め込むようにマットを入れ、すりこぎでやや固めにつめる。これで幼虫を投入する用意が整った。容器側面に大きく育ったクワガタムシ幼虫がいるのかと思うかも知れないが、これは幼虫ではなくてバナナである。色が紛らわしい。

亜終齢幼虫を容器に1頭ずつ入れていく。この後もぐり込みやすいようにマットをかき分けてやった。

ビンの底に向かっておりていく亜終齢幼虫。できればバナナが黒くなってしまわないうちにバナナを食べるところが見られると良いね。

フタをしておしまい。
昆虫フォーラムや史嶋桂さんのHPではマットは発酵させていないものを使用していた。しかしバナナがマットを発酵させるという考えならば、発酵済のマットを使用する方が効果的ではないかと私は考えている。
さて先に述べた昆虫フォーラムでは、バナナマットは皮付きのままマットに埋めるというふうに書いてあったのだが、バナナの栄養効果を早く発揮させたいために私はこれまでも皮を剥いたバナナで行ってきた。この場合バナナが古くなってドロドロになると容器内が水分過多になるので、心配な人は皮付きにするか発酵マットを少し乾かしてから使うといいだろう。とはいえ中が水分過多になってもノコギリクワガタやヒラタクワガタなら全く問題はない。今回はオオクワガタでなおかつ皮むきのバナナで、マットの水分がやや高いので気になるが、バナナが古くなると見かけ上の容積が減るので、そうなってからマットを継ぎ足せば良いだけの話だと思っている。2ヶ月くらいしたら改めてバナナマットを再セット、蛹化のタイミングが微妙であればバナナなしのマットに移すか、前蛹中期以降に人口蛹室に移せば良い。
久しぶりの昆虫ネタでブログを書くのは楽しい。
核時代68年03月24日 Bebê
さてもう1セットのオオクワガタは、上記と同じように飼育していたのだが、いずれも亜終齢幼虫だった。数は11頭。手元の発酵マットが微妙に足りなさそうだったので、バナナマット飼育をすることにした。
バナナマット飼育とは、かつてパソコン通信の@Niftyにあった昆虫フォーラムで紹介されたものである。考案者は茗荷谷博士、追試を行ったのが史嶋桂さんだった。このフォーラムには勝手に昆虫フォーラムをライバル視していた別のフォーラムの「論客」がいて、面白く画期的な取り組みには茶々を入れて邪魔をし、建設的な議論になるのを妨害する輩がいた。やってもみないであんなモノは駄目だ、などという前に面白そうだからやってみようかな、という態度こそこのフォーラムにふさわしいはずで、実は私もヒラタクワガタ・ノコギリクワガタ・コクワガタで行い、納得できる成果が出た。要はいかに大きな成虫になるかということなのだが、結論からすると菌糸ビンには敵わないと思う。しかし無添加無発酵のマットに較べれば格段に大きく育つ。発酵マットとはかなり良い勝負になる。そこで私は折衷案をとって、バナナと発酵マットの組み合わせで、なかなか得難い大きさの成虫を羽化させ、喜んだものだ。
ではバナナマットとはどういうものか。これはクワガタムシの菌床飼育がまだまだコスト高だった時代に、初心者には難しかったのかも知れない発酵マット作成のリスクを避けるために、いくつかのマット飼育が試みられた。南方に移民した日本人が、漬け物を食べたいと思っても安定した発酵が得られないので、やむを得ずバナナをぬかどこにして発酵させた、という事実がヒントになっている。したがってこの時点ではマットを発酵させるためにバナナを使うという動機であった。そのあたりを詳しく記した史嶋桂さんのホームページがアクセス不能になっているので、事実上この飼育方法を紹介したものはなさそうだ。そこで手順を踏みながら以下に紹介してみる。
黄色いコンテナに入っているのはクヌギの廃ほだマットを小麦粉で発酵させたもの。これを容器の底に固めにつめておく。
小型の傷物のバナナ。定価以下で売っているもので十分。昔は傷物というと中身まで黒くなったものが売られていたものだが.....。
皮を剥いたバナナは充分きれいなものだった。だが傷物というにはまだ熟してもいないので、人の口にはあまり美味しくないかも知れない。
11頭の幼虫に対し用意できたバナナが10本だったので、適当にカットしておおよそ同じ分量になるようにバナナを分けて容器に入れる。
バナナを埋め込むようにマットを入れ、すりこぎでやや固めにつめる。これで幼虫を投入する用意が整った。容器側面に大きく育ったクワガタムシ幼虫がいるのかと思うかも知れないが、これは幼虫ではなくてバナナである。色が紛らわしい。
亜終齢幼虫を容器に1頭ずつ入れていく。この後もぐり込みやすいようにマットをかき分けてやった。
ビンの底に向かっておりていく亜終齢幼虫。できればバナナが黒くなってしまわないうちにバナナを食べるところが見られると良いね。
フタをしておしまい。
昆虫フォーラムや史嶋桂さんのHPではマットは発酵させていないものを使用していた。しかしバナナがマットを発酵させるという考えならば、発酵済のマットを使用する方が効果的ではないかと私は考えている。
さて先に述べた昆虫フォーラムでは、バナナマットは皮付きのままマットに埋めるというふうに書いてあったのだが、バナナの栄養効果を早く発揮させたいために私はこれまでも皮を剥いたバナナで行ってきた。この場合バナナが古くなってドロドロになると容器内が水分過多になるので、心配な人は皮付きにするか発酵マットを少し乾かしてから使うといいだろう。とはいえ中が水分過多になってもノコギリクワガタやヒラタクワガタなら全く問題はない。今回はオオクワガタでなおかつ皮むきのバナナで、マットの水分がやや高いので気になるが、バナナが古くなると見かけ上の容積が減るので、そうなってからマットを継ぎ足せば良いだけの話だと思っている。2ヶ月くらいしたら改めてバナナマットを再セット、蛹化のタイミングが微妙であればバナナなしのマットに移すか、前蛹中期以降に人口蛹室に移せば良い。
久しぶりの昆虫ネタでブログを書くのは楽しい。
核時代68年03月24日 Bebê
Posted by Bebê at 09:29│Comments(6)
│オオクワガタ幼虫飼育
この記事へのコメント
懐かしい飼育方法、楽しく拝見しました。当時、私もこの方法を試したことが有りますが、なかなか優秀な方法だったと思います。
現在でも添加剤飼育(一般の市販菌糸類やマット類すべて)が主流ですが、バナナは単純にクワガタ類に必要な栄養がバランスよく揃っているので、基本的な考え方は「バナナを添加剤として利用して効果が出ている」という風に個人的な解釈をしています。
私は更にバナナパワーを引き出すために、盛夏、輪切りにしたバナナを天日干にして乾燥させ、ビタミンを蓄えさせたうえで、バナナチップとして発酵マットや菌糸ビンに埋め込んだりしています。
添加剤としての結果、主流の麦芽やキトサンと比較して優秀なのかどうかというところまではわかりませんが、自分で添加剤を作ってみたということ自体が面白く、今でも時々準備をします。
現在でも添加剤飼育(一般の市販菌糸類やマット類すべて)が主流ですが、バナナは単純にクワガタ類に必要な栄養がバランスよく揃っているので、基本的な考え方は「バナナを添加剤として利用して効果が出ている」という風に個人的な解釈をしています。
私は更にバナナパワーを引き出すために、盛夏、輪切りにしたバナナを天日干にして乾燥させ、ビタミンを蓄えさせたうえで、バナナチップとして発酵マットや菌糸ビンに埋め込んだりしています。
添加剤としての結果、主流の麦芽やキトサンと比較して優秀なのかどうかというところまではわかりませんが、自分で添加剤を作ってみたということ自体が面白く、今でも時々準備をします。
Posted by ふうけぃ☆風敬 at 2013年03月31日 18:00
*ふうけぃ☆風敬さん*
ご無沙汰しております。ふうけぃさんもバナナマットを試しておられたのですか。バナナを乾燥させるというところがさすがの創意工夫ですね。次に幼虫が採れた時には試してみましょう。今年の夏に繁殖可能なクワガタムシ成虫はいないので、コクワガタかノコギリクワガタを採らないといけないかな。楽しみにしておきます。
ご無沙汰しております。ふうけぃさんもバナナマットを試しておられたのですか。バナナを乾燥させるというところがさすがの創意工夫ですね。次に幼虫が採れた時には試してみましょう。今年の夏に繁殖可能なクワガタムシ成虫はいないので、コクワガタかノコギリクワガタを採らないといけないかな。楽しみにしておきます。
Posted by Bebê at 2013年03月31日 19:06
at 2013年03月31日 19:06
 at 2013年03月31日 19:06
at 2013年03月31日 19:06ご無沙汰しております。ホームページを拝見するとクワガタでしたので、さっそく書かせていただいています。
バナナマット、どの成分が効果があるのか興味深いです。単純に糖質が微生物活動のエネルギー源になるのか、それとも微量成分に効果のあるものがあるのかなど・・。
いずれにしても、結果を楽しみにいたします。
バナナマット、どの成分が効果があるのか興味深いです。単純に糖質が微生物活動のエネルギー源になるのか、それとも微量成分に効果のあるものがあるのかなど・・。
いずれにしても、結果を楽しみにいたします。
Posted by くらさん at 2013年04月04日 23:20
*くらさん*
こちらこそご無沙汰しております。バナナの何が利くのか、というのはぜひ解明したいところです。だいぶ前のこと、風邪をこじらして下痢が続いていた時に病院で見たチラシに、そういう時はバナナを食べてはいけないという意味のことが書かれていました。胃腸の中で発酵してしまい、それが悪さをするのだそうです。人の場合は手軽なエネルギー補給源になるのですが、オオクワガタではどうでしょうね。
昨夜見たところでは、大きく育った亜終齢幼虫のビンはバナナがかなり食べられているようです。逆にあまりよく育っていない幼虫のビンには、バナナのあたりから白いカビが発生していました。幼虫が活発に動き出せばこれらのカビは消えていくので、今のところは心配しておりません。
終齢幼虫になって育ち具合が良く分かるようになれば良いなと感じています。
こちらこそご無沙汰しております。バナナの何が利くのか、というのはぜひ解明したいところです。だいぶ前のこと、風邪をこじらして下痢が続いていた時に病院で見たチラシに、そういう時はバナナを食べてはいけないという意味のことが書かれていました。胃腸の中で発酵してしまい、それが悪さをするのだそうです。人の場合は手軽なエネルギー補給源になるのですが、オオクワガタではどうでしょうね。
昨夜見たところでは、大きく育った亜終齢幼虫のビンはバナナがかなり食べられているようです。逆にあまりよく育っていない幼虫のビンには、バナナのあたりから白いカビが発生していました。幼虫が活発に動き出せばこれらのカビは消えていくので、今のところは心配しておりません。
終齢幼虫になって育ち具合が良く分かるようになれば良いなと感じています。
Posted by Bebê at 2013年04月05日 14:01
at 2013年04月05日 14:01
 at 2013年04月05日 14:01
at 2013年04月05日 14:01 バナナマット、私はまだ試したことはありません。これから発酵マットを仕込もうか、それとも少し購入しようか、と迷っているところなのですが、発酵マットの自作・購入にかかわらず、バナナマットを少し試してみたいと思いました。
写真が入ると良いですね!
写真が入ると良いですね!
Posted by たら at 2013年04月08日 00:25
*たらさん*
コメントありがとうございます。私は幼虫飼育の温度管理はせずになすがままですが、この時期に亜終齢幼虫がいるということ自体珍しいです。バナナマットはどちらかと言うと暖かい〜暑い時期に向くかも知れませんね。幼虫が一生懸命マットを食べて大きくなる過程が良いと思います。今は活発に食べている個体もいますが、そうでない個体のビンにはバナナのあたりから白カビ・青カビが出てきています。幼虫がいるあたりにはそれらが届かないというのは面白いことです。今後暖かくなって食が活発になればやがてカビは消えていきます。
バナナマットでの飼育は面白いですから、是非一度試してみて下さい。
コメントありがとうございます。私は幼虫飼育の温度管理はせずになすがままですが、この時期に亜終齢幼虫がいるということ自体珍しいです。バナナマットはどちらかと言うと暖かい〜暑い時期に向くかも知れませんね。幼虫が一生懸命マットを食べて大きくなる過程が良いと思います。今は活発に食べている個体もいますが、そうでない個体のビンにはバナナのあたりから白カビ・青カビが出てきています。幼虫がいるあたりにはそれらが届かないというのは面白いことです。今後暖かくなって食が活発になればやがてカビは消えていきます。
バナナマットでの飼育は面白いですから、是非一度試してみて下さい。
Posted by Bebê at 2013年04月08日 10:05
at 2013年04月08日 10:05
 at 2013年04月08日 10:05
at 2013年04月08日 10:05